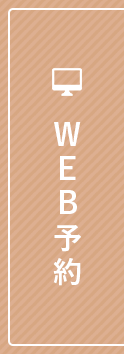歯の数や構造、かたち、色の異常
2025年6月25日
歯もからだの成長と同様に成長していきます。歯は顎の骨の中で育つため、目で直接見ることはできません。顎の中でずっと成長を続け、準備ができると次第に口の中に現れてきます。乳歯だったら歯が全く無い歯ぐきに生えてきますし、永久歯であれば乳歯がグラグラして永久歯に生え変わりますね。
しかし、歯の成長途中に何らかの悪影響が生じると、歯の数やかたち、構造などに異常が現れることがあります。今回はそのような歯のさまざまな異常についてご説明していきます。
【歯の数の異常】
通常、生えてくるはずの歯の数が足りなかったり、過剰だったりして異常が認められることがあります。
・完全無歯症(かんぜんむししょう)
歯が全くない状態です。
非常に稀なケースですが、先天的に歯が一本も生えてこない場合があります。
無歯症は、外胚葉異形成症(がいはいよういけいせいしょう)という先天的な疾患の一症状として現れることが多く、この病気では歯以外にも、毛髪や爪、汗腺に異常が生じることがあります。
・先天性欠如(せんてんせいけつじょ)
生まれつき歯の本数が少ない状態を指します。これは部分的無歯症とも呼ばれ、特に第二小臼歯(前から5番目の歯)や側切歯(前から2番めの歯)に多く見られます。実際には、10人に1人程度の割合で起こる比較的よく見られます。遺伝なども影響を与える因子です。
・過剰歯(かじょうし)
歯の本来の数は乳歯20本、永久歯28~32本です。
過剰歯は通常の葉が生える本数よりも、過剰に多く作られた歯のことを意味します。
普通の歯と同様に生えてくることもありますが、骨の中で埋まったままになっていることもあります。骨の中にある場合は、レントゲンを撮ったら過剰歯があることに気づくことができます。
かたちとしては、基本的には奇形の歯ですので、普通の歯と違っていたり大きさも異なっています。三角錐のような形をしていたり、小さかったりとさまざまです。多くの場合は抜歯となるでしょう。
【歯の構造に関する異常】
歯はエナメル質や象牙質という層で覆われていて神経を守っているのですが、その歯を構成しているエナメル質や象牙質がきちんと作られていない状態を指します。
・エナメル質形成不全症(MIH)
エナメル質形成不全症は、歯の表面を覆うエナメル質が十分に形成されない状態を指します。症状として、エナメル質が薄くなったり、部分的に欠けることがあり、歯が黄色く見えることが多いです。エナメル質が不十分だと、歯がむし歯になりやすくなるため、注意が必要です。
・象牙質形成不全症
象牙質形成不全症は、歯の内部にある象牙質が正常に作られない状態です。この異常では、歯が琥珀色に変わりやすく、象牙質とエナメル質の結合力が弱いため、歯が欠けやすくなります。さらに、象牙質がしっかり作られないため、歯の根が短くなることもあります。
・歯内歯
歯内歯とは、歯の内部にエナメル質や象牙質が過剰に入り込んでしまう異常です。特に上顎の側切歯(上の前から2番めの歯)に多く見られ、形状が通常と異なるため、むし歯や歯周病のリスクが高まることがあります。

【歯のかたちに関する異常】
歯には歯の種類によってそれぞれ決まったかたちがありますが、通常とは異なる様子を呈します。
・ハッチンソンの歯
ハッチンソンの歯は、生まれつき梅毒に感染していた場合に、子どもの歯に見られる形状の異常です。この症状では、前歯の縁に半月状のくぼみができ、歯の横幅が通常よりも狭くなることが特徴です。
・矮小歯
矮小歯は、通常よりも小さな歯です。隣の歯に比べると明らかに小さいので見分けがつきやすいかもしれません。歯の大きさだけでなく、形状も異なることが多く、特に尖った形をした円錐歯や、細長い栓状歯などの形状異常が見られることがあります。これらの異常は見た目の問題だけでなく、かみ合わせや口腔機能にも影響を及ぼす場合があります。
・巨大歯
通常の歯よりも著しく大きな歯です。特に前歯や奥歯に見られ、歯冠の大きさや歯根の長さが通常の歯と比べて大きくなります。かみ合わせに問題を引き起こすことが多いため、矯正治療が必要となる場合があります。
・双生歯(そうせいし)
一つだった歯胚(歯のもとになるもの)が何らかの原因で2つに分離してしまい、そのまま成長発育した歯です。
・エナメル滴
歯の根元部分に球状の隆起ができる状態で、エナメル真珠とも呼ばれます。この異常は、歯周組織との密着が不十分になり、歯周病の原因となることがあります。定期的な検診での早期発見と予防が重要です。
【歯の色に関する異常】
・斑状歯(はんじょうし)
斑状歯は、フッ素の過剰摂取によって引き起こされる歯の色の異常です。
1~2ppm以上のフッ化物を長期間摂取した場合に、歯に水平な白色や褐色の斑点が現れます。この症状は、むし歯予防の効果がフッ素によって発見されるきっかけとなった現象でもありますが、適量のフッ素は安全ですので、日常の歯みがきに使用する場合は心配いりません。
(歯科医院でのフッ素塗布や家庭で使用する高濃度のフッ素配合歯磨剤などは安全です。)
・テトラサイクリンの副作用
テトラサイクリンという抗菌薬を歯が形成される時期に服用すると、象牙質に影響を与え、歯に灰色や茶色のしま模様が現れることがあります。
【その他の異常】
・歯牙腫
歯牙腫は、歯胚が過剰に発育することで形成される良性の腫瘍です。
歯の構造が含まれており、痛みや腫れなどの自覚症状もありません。定期検診などのレントゲン撮影によって発見されることが多いです。

【OCEAN歯科からのメッセージ】
歯の異常といってもいろいろな種類があります。
歯の発育不足や過剰による異常は、歯の数、かたち、色、構造にさまざまな影響を及ぼします。これらの異常は、先天的な要因や環境要因によって引き起こされることが多く、適切な診断と治療が必要となることもあります。
もしも気になることなどがあれば、お気軽にご相談ください。
むし歯になりやすい人と部位、その予防方法
2025年6月10日
むし歯は多くの人が経験する口腔の問題ですが、なぜ同じような生活習慣を送っていてもむし歯になりやすい人とそうでない人がいるのでしょうか?むし歯は単なる口のトラブルではなく、生活習慣や体質、歯の状態などさまざまな要因が絡み合って発生します。今回は、むし歯になりやすい人の特徴やむし歯ができやすい部位、そしてそれらを予防するための具体的な方法について詳しく解説していきます。
【むし歯になりやすい人の特徴】
①食生活が不規則
食生活の乱れは、むし歯のリスクを大きく高める要因です。特に、間食を頻繁に摂ったり、糖分を多く含む飲み物やお菓子を常に摂取していると、口腔内の環境が悪化します。食事と食事の間に糖分を摂取すると、口腔内のpHが酸性に傾き、むし歯を引き起こす原因となります。酸性環境では、歯のエナメル質が溶けやすくなり、むし歯が進行しやすくなります。
具体例として、夜遅くにお菓子を食べる習慣がある場合、就寝中に口腔内に糖分が残り、むし歯のリスクが増します。甘いものを摂取した後は、できるだけ早く歯みがきをすることが重要です。
②歯みがきが不十分
むし歯の予防には、適切な歯みがきが欠かせません。しかし、歯みがきが不十分な場合、歯垢(プラーク)が溜まりやすくなり、虫歯や歯周病の原因となります。歯垢は細菌の温床であり、これが口腔内に長時間残ると、酸が生成されて歯を溶かします。特に、歯ブラシが届きにくい歯と歯の間や奥歯の隙間に歯垢がたまりやすいです。
歯みがきの際には、歯と歯ぐきの境目を意識して、軽い力で磨くことが大切です。また、歯ブラシだけでは完全に取り除けない歯垢もあるため、フロスや歯間ブラシを併用することをおすすめします。
③唾液の分泌が少ない
唾液は口腔内の健康を保つために非常に重要です。唾液には、口腔内の酸を中和する役割や、食べ物の残りカスを洗い流す作用があります。唾液の分泌が少ないと、口腔内が乾燥し、むし歯や口臭のリスクが高まります。
唾液の分泌を促進するためには、よくかんで食事をすることが効果的です。食事をすると唾液の分泌が自然に促されます。また、水分をしっかり摂ることや、シュガーレスのガムをかむことも唾液の分泌を助ける方法です。
④歯並びが悪い
歯並びが悪いと、歯の間に食べ物が詰まりやすくなり、歯みがきが難しくなります。特に、歯が重なっていたり、隙間が不規則な場合は、歯ブラシが届きにくく、歯垢が溜まりやすいです。その結果、むし歯や歯周病のリスクが高まります。
歯並びが気になる場合は、矯正治療を検討することも一つの方法です。矯正治療によって、歯の位置が整い、むし歯や歯周病のリスクが低くなる場合があります。
【虫歯になりやすい部位】
①歯と歯の間
歯と歯の間は、歯ブラシが届きにくく、食べ物のカスが溜まりやすい場所です。この部位は、むし歯が発生しやすく、初期の段階では痛みを感じにくいため、気づかないうちに進行することがあります。定期的にフロスや歯間ブラシを使って、歯と歯の間をしっかりと清掃することが重要です。
フロスを使う際は、優しく歯と歯の間に挿入し、前後に動かして汚れを取り除きます。歯間ブラシも効果的ですが、サイズが合わないと歯肉を傷つける可能性があるため、適切なサイズを選ぶことが大切です。
②奥歯の溝
奥歯の咬合面(噛む面)には深い溝があり、ここに食べ物が詰まりやすく、むし歯ができやすいです。特に、乳歯や永久歯が生えたばかりの時期は、溝が深く、歯ブラシだけでは十分に清掃できないことがあります。
予防策としては、歯科医院でのフッ素塗布やシーラント処置を検討することが有効です。シーラントは、奥歯の溝に薄い樹脂を塗布することで、虫歯の原因となる食べ物のカスがたまりにくくします。
③歯の根元
歯の根元部分は、歯茎が下がることで露出しやすくなります。ここが露出すると、むし歯や知覚過敏が起こりやすくなります。根元が露出する原因としては、歯周病や過度のブラッシングがあげられます。
根元が露出している場合、ブラッシング時には優しくみがくことが重要です。また、デンタルケア製品には、知覚過敏用の歯磨き粉や、歯の根元を保護する成分が含まれているものもありますので、適切な製品を選ぶことが大切です。

【むし歯の予防方法】
①正しい歯みがき習慣
むし歯予防には、毎日の歯みがきが欠かせません。歯ブラシは柔らかめのものを選び、歯と歯茎の境目を意識して丁寧にみがきます。一般的には、1回の歯みがきにつき2分以上かけることが推奨されます。歯磨き粉にはフッ素が含まれているものを選ぶと、エナメル質の強化が期待できます。
歯みがきの順番としては、まず奥歯から始め、前歯に移ると良いでしょう。奥歯は特に汚れがたまりやすい部分なので、丁寧にみがくことが重要です。また、歯みがきだけでなく、舌の清掃も忘れずに行いましょう。舌にたまる細菌も口臭の原因になります。
②定期的な歯科検診
定期的な歯科検診は、むし歯や歯周病の早期発見に役立ちます。通常、3~6ヶ月ごとに歯科医院を訪れることが推奨されます。検診では、歯科医師が口腔内を詳しくチェックし、問題がないか確認します。また、プロフェッショナルなクリーニングも行われ、歯垢や歯石が取り除かれます。
検診を受けることで、自分では気づかなかった小さなむし歯や歯の問題も早期に発見され、適切な治療やアドバイスが受けられます。定期的な検診を受けることで、長期的に口腔の健康を維持することができます。
③食生活の見直し
むし歯予防には、食生活の見直しが重要です。糖分の多い食べ物や飲み物は、むし歯のリスクを高めるため、控えめにしましょう。特に、砂糖が多く含まれるお菓子やジュースを頻繁に摂取することは、むし歯の原因となります。
バランスの取れた食事を心がけることも大切です。食物繊維が豊富な野菜やフルーツを摂取することで、口腔内の健康をサポートできます。また、食後に水を飲むことで、口腔内の酸を中和し、虫歯のリスクを減らすことができます。
④唾液の分泌を促す方法
唾液の分泌を促進するためには、よくかんで食事をすることが効果的です。食事をしっかりかむことで唾液の分泌が促され、口腔内の自浄作用が高まります。さらに、シュガーレスのガムをかむことで唾液の分泌を促進することができます。
唾液の分泌が少ないと感じる場合は、口腔内を乾燥させないように水分をしっかり摂ることも大切です。特に、口の乾燥を感じる場合は、こまめに水を飲むように心がけましょう。また、口腔内の乾燥を改善するための製品も市販されていますので、適宜使用するのも良いでしょう。

【OCEAN歯科からのメッセージ】
むし歯は、誰にでも起こりうる口腔の問題ですが、日々のケアと予防をしっかりと行うことで、そのリスクを大きく減らすことができます。自分の生活習慣や口腔内の状態に合わせた予防方法を取り入れ、健康な歯を維持していきましょう。定期的な検診と適切なケアが、長期的な口腔の健康を保つ鍵となります。今日から実践して、むし歯のリスクを減らしていきましょう。